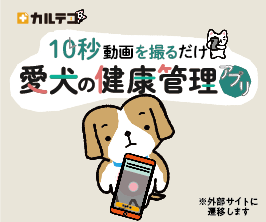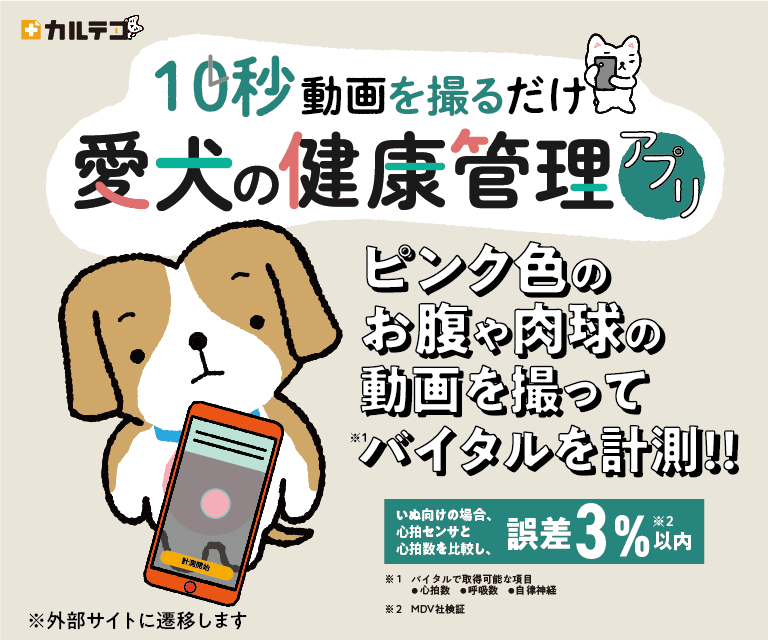大切なペットとの暮らしのためのお役立ち情報
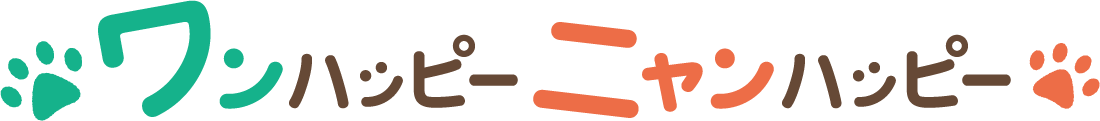
犬の生活
犬のペット保険の選び方!比較ポイントや注意点など実例を交えて徹底解説

ペット保険とは?
犬を飼っていると、一度は「ペット保険」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。でも実際にどういったものなのか、なんとなくしか知らない人も多いのではないでしょうか。ここでは、ペット保険の基本的な仕組みとその役割についてわかりやすく説明します。
人間の医療保険との違い
ペット保険は、人間でいう健康保険に似た仕組みを持っていますが、最大の違いは公的制度ではないという点です。日本では動物に健康保険制度がないため、すべての医療費が自己負担になります。そのため、ちょっとしたケガや病気でも高額な診療費がかかることがあります。
補償のしくみと負担軽減のメリット
ペット保険に加入していれば、治療費の一部を保険会社が負担してくれます。補償の割合は50%~90%などさまざまで、プランにより選べます。たとえば、診察代や投薬費、手術代といった医療費のうち保険がカバーする部分を除いた金額だけを飼い主が支払えば済むという仕組みです。
通院・入院・手術それぞれに対応した保険も
保険によっては通院のみ対象のものもあれば、入院や手術にもしっかり対応しているものもあります。愛犬がどんな健康リスクにさらされやすいかを踏まえて、自分の家庭に合った補償内容を選ぶことが大切です。
支払方法や請求手続きの違いもチェック
ペット保険の中には、病院でそのまま保険が使える「窓口精算」タイプもありますが、多くの場合は一度全額を立て替えて後から保険会社に請求する「後日精算」方式です。加入前に精算方法を確認しておくと安心です。
犬にペット保険が必要な理由

可愛い愛犬との暮らしは幸せな時間そのものですが、ふとした拍子に病気やケガに見舞われることもあります。犬の医療費は思っている以上に高額になるケースが多く、備えとしてペット保険を検討する人が増えています。ここでは、なぜ犬にペット保険が必要なのか、現実的な視点からお話ししていきます。
犬の医療費は「全額自己負担」
日本では犬の診療費に公的保険は適用されないため、治療にかかる費用はすべて飼い主の負担です。風邪のような軽い症状であっても、診察料や薬代で数千円はかかりますし、手術や入院が必要になれば数十万円にのぼることも珍しくありません。
犬がかかりやすい病気やケガが多い
犬種や年齢によってリスクの高い病気は異なります。たとえば小型犬には膝蓋骨脱臼や気管虚脱、大型犬には股関節形成不全や胃捻転などがよく見られます。誤飲や交通事故といった突発的なトラブルも含めると、どんな犬でも何かしらの健康トラブルに見舞われる可能性は十分にあります。
高齢になるほどリスクも医療費も増加
犬も年齢を重ねると、慢性疾患やがんといった病気のリスクが高くなります。当然ながら治療にかかる費用や頻度も増え、通院が日常的になることもあります。高齢になる前に保険に入っておくことで、必要な医療を経済的に諦めずに済むという安心感を得られます。
「いざというとき」の判断を支える
突然の病気やケガで獣医師から高額な治療を提示されたとき、金銭的な事情で躊躇してしまうこともあるでしょう。ペット保険に入っていれば、経済的な理由で迷わずに済む可能性が高く、愛犬にとって最善の医療を選ぶための後押しになります。
犬のペット保険の選び方!比較する際の5つのポイント

犬のペット保険にはさまざまな種類があり、補償内容や料金体系も保険会社ごとに大きく異なります。たくさんある選択肢の中から、どの保険を選ぶかは悩ましいところです。ここでは、愛犬と飼い主にとって納得のいく保険を選ぶために、比較検討すべき主要なポイントを紹介します。
①補償範囲がどこまでカバーされているか
まず注目すべきは、補償の対象となる治療内容です。「通院」「入院」「手術」のすべてがカバーされているか、あるいはいずれかに限定されているかは大きな違いになります。また、特定の病気や既往症が補償対象外になる場合もあるため、細かな条件も確認しておく必要があります。
②補償割合と年間支払限度額
保険によって、治療費の補償割合が50%・70%・90%など複数から選べる場合があります。割合が高ければそのぶん自己負担は減りますが、保険料は高めになります。
また、年間でいくらまで補償されるかという「限度額」も重要です。頻繁に通院が必要になる犬にとっては、限度額が少ないと十分な補償を受けられない場合があります。
③免責金額の有無とその設定額
「免責金額」とは、一定額までは自己負担になる制度のことです。たとえば、免責が3,000円で補償割合が70%の場合、1万円の診療費がかかっても最初の3,000円は自己負担で、残りの7,000円に対して70%が補償されるという計算になります。細かな出費が多いケースでは、免責の有無が負担感に直結します。
④月額保険料とその上昇傾向
保険料は年齢によって上がるのが一般的です。若いうちは安価でも、高齢になるにつれて急激に高くなる場合もあるため、長期的な支払い計画を想定して選ぶことが大切です。毎月無理なく支払える保険料かどうかを基準に考えると、安心して継続しやすくなります。
⑤保険金請求の方法と手続きの簡便さ
保険を使う機会は突然やってきます。そのときに手続きが煩雑だと、ストレスや不安が増してしまいます。窓口精算ができるか、申請はアプリで完結できるか、必要書類は何かといった具体的な部分も確認しておくと、いざという時の安心につながります。
犬のペット保険の選ぶ際の注意点

保険の比較ポイントをしっかり押さえていても、見落としがちな点や後悔につながりやすい落とし穴は意外と多いものです。ここでは、犬のペット保険を選ぶ際に注意しておくべき具体的な点を解説します。
加入できる年齢に制限がある
多くのペット保険には加入できる年齢の上限があります。一般的には8歳~10歳前後までが多く、それを超えると新規加入ができない場合もあります。高齢になってから「やっぱり入っておけばよかった」と後悔するケースもあるため、健康な若いうちからの検討が理想的です。
既往歴があると加入や補償に制限がかかる
過去に病気やケガの治療歴があると、その部位や病気が補償対象外となることがあります。保険会社によっては診断書や通院履歴の提出を求められることもあるため、告知義務の内容をしっかり確認しておくことが重要です。
補償内容に「免責事項」が含まれることも
一見手厚く見える補償でも、「これとこれは対象外です」といった免責事項が記載されている場合があります。たとえば予防接種や去勢・避妊手術、健康診断などは基本的に補償対象外であることが多く、補償される範囲を勘違いして契約すると、思わぬトラブルに繋がる可能性があります。
高齢になると保険料が一気に上昇することも...
加入時は月々の保険料が手頃でも、年齢が上がるごとに保険料が上昇するのが一般的です。保険によっては高齢期に入ると一気に跳ね上がることもあり、継続が難しくなる場合もあります。長く続ける前提で、将来的な負担を想定しておくことが大切です。
更新時に契約内容が変わる可能性がある
毎年の更新時に補償内容が見直されることがあり、補償範囲が狭まったり、保険料が上がったりすることがあります。特に高齢犬の場合、更新が制限されるケースもあるため、契約前に「更新後の条件」がどうなるか確認しておくと安心です。
犬のペット保険選びでよくある質問(Q&A)

ペット保険について調べていると、さまざまな疑問が浮かんでくるものです。ここでは、実際に多くの飼い主が抱く代表的な質問にQ&A形式でお答えします。
Q. 高齢の犬でも保険に入れますか?
A:多くの保険会社では新規加入の年齢制限があります。上限は8歳~10歳程度が一般的です。ただし、すでに加入していれば高齢になっても継続は可能な場合が多いです。高齢になってからでは遅いこともあるため、若いうちの加入が安心です。
Q. すでに持病がある犬も加入できますか?
A:加入はできる場合もありますが、既往症やその関連疾患が補償対象外になるケースが多いです。保険会社によっては診療履歴の提出が必要で、条件付きでの加入になることもあるため、事前の確認が必要です。
Q. 去勢・避妊手術は保険でカバーされますか?
A:一般的に、去勢・避妊手術は予防医療に該当するため、ほとんどの保険では補償対象外となります。ただし、まれに補償対象として含まれる特別なプランもあるため、加入前に保険の細かい条件を確認しておくとよいでしょう。
Q. 保険料は年齢によって変わりますか?
A:はい、多くの保険では年齢に応じて保険料が段階的に上がっていきます。特に高齢期になると急激に保険料が上昇する傾向があるため、長く加入するつもりなら、将来の負担も視野に入れて選ぶことが大切です。
Q. 一度使ったら保険料が上がることはありますか?
A:人間の自動車保険とは異なり、ペット保険では一般的に保険を使ったからといって翌年の保険料が上がることはありません。ただし、更新時に補償内容や条件が変更されることがあるので、定期的に見直しをしておくことをおすすめします。
まとめ

犬のペット保険は、愛犬との生活を安心して続けるための大切な備えです。病気やケガは予想もつかないタイミングでやってきますし、そのたびに大きな出費を求められることも少なくありません。ペット保険に入っていれば、経済的な不安にとらわれずに、治療の選択肢を広げることができます。
保険を選ぶ際には、補償範囲や割合、保険料、加入条件、請求方法など多角的な視点で比較することが大切です。特に見落とされがちな「免責事項」や「更新時の条件変更」なども、加入前にしっかりチェックしておくことで、後悔のない選択につながります。
また、加入のタイミングも重要です。若いうちから備えることで、加入条件が有利になるだけでなく、万が一の事態にも冷静に対応しやすくなります。愛犬の将来を見据えて、無理のない範囲で保険を検討してみてください。
記事の提供/わんちゃんホンポ
【「わんちゃんホンポ」について】
「わんちゃんホンポ」は株式会社ピーネストジャパンが運営する「犬」に特化した情報を配信する、ドッグオーナーさん向けポータルサイトです。ドッグオーナーさんとその愛犬自身の生活環境がより良く素敵なものになることを目指し、「しつけやお手入れのハウツー」「犬の病気や健康に関する情報」「犬に関連する最新のニュース」など、わんちゃんに関連する様々な情報を配信しております。
※掲載している内容は、2025年7月17日時点のものです。
※ページ内のコンテンツの転載を禁止します。