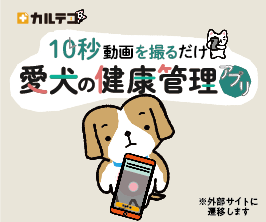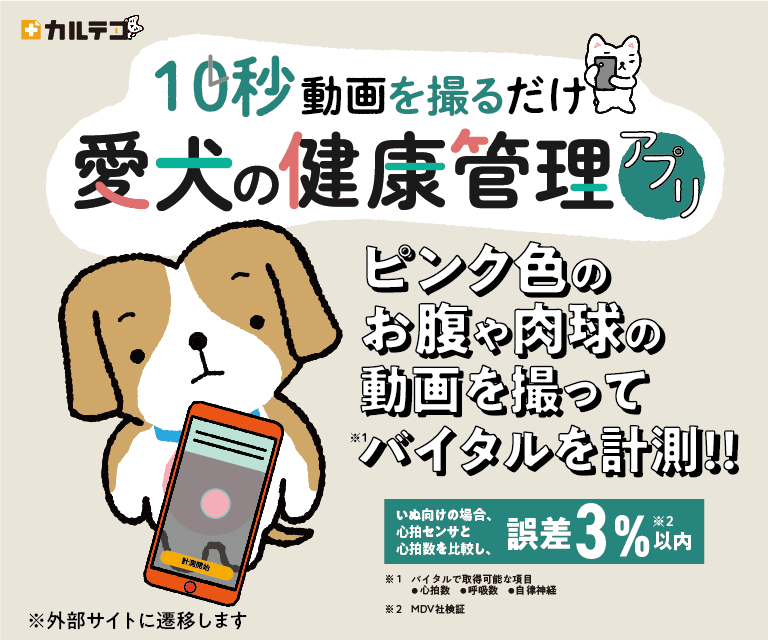大切なペットとの暮らしのためのお役立ち情報
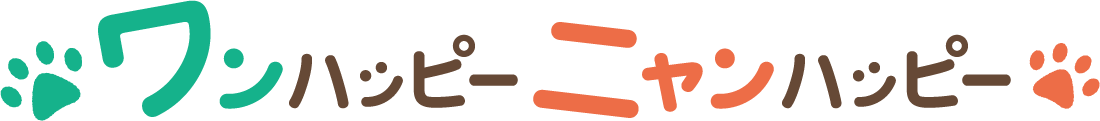
猫の生活
【獣医師監修】猫の避妊・去勢とは?手術のメリット・デメリット、適した時期や費用まで徹底解説

目次
猫の避妊・去勢とは?
猫の避妊・去勢手術は、将来の繁殖を防ぐために行われる外科的な処置です。性別によって手術の内容が異なります。
メス猫の避妊手術
メス猫に行うのは「避妊手術」です。一般的には、開腹して卵巣と子宮を摘出する「卵巣子宮摘出術」が行われます。この手術により、妊娠しなくなるだけでなく、発情期特有の行動や、子宮に関連する病気を防ぐことができます。
オス猫の去勢手術
オス猫に行うのは「去勢手術」です。精巣(睾丸)を摘出する「精巣摘出術」が一般的です。メス猫の開腹手術に比べると、体への負担が少ない手術とされています。この手術により、繁殖能力をなくし、スプレー行動などのマーキングや、他の猫との縄張り争いを減らす効果が期待できます。
猫を避妊・去勢するメリットとデメリット

手術には、心身両面におけるメリットがある一方で、飼い主として理解しておくべきデメリットも存在します。両方を正しく理解し、総合的に判断することが重要です。
避妊・去勢手術の「メリット」
手術を行うことで得られるメリットは、猫と飼い主の双方にとって大きなものです。
望まない繁殖の防止
最大のメリットは、望まない子猫が生まれるのを確実に防げることです。猫は非常に繁殖力が強い動物であり、一回の出産で4~8頭の子猫を産むこともあります。すべての子猫に責任を持つことは大変なことであり、不幸な最期を迎える可能性を未然に防ぎます。
発情期特有の行動の抑制
発情期に見られる特有の行動を大幅に減らすことができます。メス猫の大きな鳴き声や、オス猫のマーキング(スプレー行動)や攻撃性の高まり、脱走などは、猫にとっても飼い主にとっても大きなストレスとなります。これらの行動が抑制されることで、より穏やかな共同生活を送れるようになります。
生殖器関連の病気リスクの低減
将来起こりうる様々な病気のリスクを大幅に下げることができます。メス猫では、乳腺腫瘍や子宮蓄膿症といった命に関わる病気の発生率が著しく低下します。特に乳腺腫瘍は、初回発情前に避妊手術を行うことで、発生リスクを90%以上抑制できるというデータもあります。オス猫では、精巣腫瘍や前立腺肥大などの病気を予防できます。
これらの病気は治療費も高額になりやすいものも多く、罹患した場合には飼い主の負担も大きくなりやすいです。あくまで一例ですが、以下が実際に請求のあった事例となります。
| 病名 | 子宮蓄膿症 |
|---|---|
| 猫種 | ミックス(雑種) |
| 年齢 | 1歳 |
| 内容 | ・入院 ・血液検査 ・レントゲン検査 ・手術 ・超音波検査 ・病理検査 など |
| 手術費(1回) | 298,961円 |
| 入院費(4日) | 10,700円 |
| 通院費(0日) | 0円 |
| 合計 | 309,661円 |
※こちらの診療費は参考例です。実際の診療費などは病院によって異なります。
※2025年3月に実際にあった事例になります。
| 病名 | 乳腺腫瘍 |
|---|---|
| 猫種 | ミックス(雑種) |
| 年齢 | 16歳 |
| 内容 | ・入院 ・点滴 ・手術 ・血液検査 など |
| 手術費(1回) | 283,529円 |
| 入院費(5日) | 16,500円 |
| 通院費(0日) | 0円 |
| 合計 | 300,029円 |
※こちらの診療費は参考例です。実際の診療費などは病院によって異なります。
※2025年1月に実際にあった事例になります。
避妊・去勢手術の「デメリット」
メリットがある一方で、飼い主が理解し、受け入れるべき点も存在します。
全身麻酔のリスク
どのような手術であっても、全身麻酔にはリスクが伴います。しかし、現代の動物医療では、事前の術前検査によって猫の健康状態を詳細に把握し、個々の猫に合わせた麻酔薬を選択することで、そのリスクは最小限に抑えられています。
二度と繁殖できなくなること
手術を行うと、当然ながらその猫は繁殖能力を失います。もし将来的に愛猫の子孫を残したいと考えている場合は、手術は慎重に判断する必要があります。
肥満になりやすくなる傾向
手術後は、性ホルモンの分泌がなくなることで基礎代謝が低下し、食欲が増す傾向があります。そのため、これまでと同じ食事内容では太りやすくなります。肥満は関節炎や糖尿病など、様々な病気の引き金となるため、飼い主による適切な食事管理が不可欠です。
避妊・去勢手術後の猫の変化について

手術後、猫の行動や体にはいくつかの変化が見られることがあります。これは主にホルモンバランスの変化によるもので、多くの場合は良い方向への変化です。
行動や性格の変化
性的なストレスから解放されることで、性格が穏やかになる傾向があります。特にオス猫では、縄張り意識や攻撃性が緩和され、他の猫や家族に対してより友好的になることがあります。前述の通り、発情期に見られた大きな鳴き声やスプレー行動といった問題行動もほとんど見られなくなります。
食欲と体重の変化
多くの場合、手術後は食欲が増加します。これは、活動に必要とされるエネルギー量が減る一方で、食欲をコントロールしていたホルモンが減少するためです。この変化を知らずに食事を与えすぎると肥満につながるため、術後は体重の変化を注意深く観察し、必要に応じて獣医師と相談の上、低カロリーの術後ケア用フードなどに切り替えるといった対策が重要になります。
猫の避妊・去勢の適した時期はいつから?

手術の時期は、猫の健康と病気の予防効果に大きく関わります。一般的に推奨されているのは、最初の発情を迎える前である「生後6ヶ月前後」です。
この時期に手術を行うことで、前述した乳腺腫瘍などの病気の予防効果を最大限に高めることができると考えられています。
ただし、猫種や成長の度合いによる個体差もあるため、これが絶対的な基準ではありません。最近では、より早期(生後3~4ヶ月齢)での手術を推奨する考え方もあります。
愛猫にとって最適なタイミングを判断するためには、かかりつけの動物病院の獣医師とよく相談することが最も大切です。
猫の避妊・去勢手術の流れ

手術を受けると決めた後、どのような流れで進むのかを知っておくことで、飼い主様の不安も軽減されます。
手術前の準備と診察
まず動物病院で診察を受け、手術日を予約します。手術を安全に行うため、事前に血液検査やレントゲン検査といった術前検査を実施します。
これにより、麻酔のリスクや隠れた病気がないかを確認します。手術前日の夜から、獣医師の指示に従って絶食・絶水が必要になります。これは、麻酔中に胃の内容物が逆流して気管を塞ぐ誤嚥(ごえん)を防ぐための重要な処置です。手術当日
予約した時間に猫を動物病院へ連れて行きます。猫を預けた後、鎮静処置、全身麻酔、手術という流れで進みます。
手術自体にかかる時間は、オス猫であれば比較的短時間、メス猫の開腹手術であっても通常は1時間程度で終了します。手術後は、麻酔から安全に覚醒するまで、入院室などで獣医師や動物看護師の管理下で過ごします。
退院と術後の通院
麻酔から完全に覚醒し、状態が安定していれば、日帰りまたは一泊程度の入院で退院となります。退院時には、自宅でのケアの方法や、抗生剤などの内服薬について詳しい説明があります。
抜糸が必要な場合は、手術から1~2週間後に再度通院します。近年では、体内で溶ける糸を使用し、抜糸が不要なケースも増えています。
猫の避妊・去勢手術の注意点

手術が無事に終わっても、自宅でのケアが非常に重要です。愛猫が安心して回復できるよう、環境を整えましょう。
手術後の自宅でのケア
退院後、猫はまだ本調子ではありません。まずは静かで落ち着ける場所でゆっくり休ませてあげましょう。高い場所へのジャンプは傷口に負担をかけるため、キャットタワーなどを利用している場合は一時的にステップを減らすなどの工夫が必要です。
また、猫が傷口を舐めたり噛んだりして化膿させないように、エリザベスカラーや術後服を着用させます。嫌がる場合もありますが、傷の回復のためには非常に重要なので、獣医師の指示に従いましょう。
異変に気づいたときの対応
自宅でのケア中に、食欲や元気が全くない、嘔吐を繰り返す、傷口がひどく腫れている、出血や膿が出ているといった異常が見られた場合は、自己判断せず、すぐに手術を受けた動物病院に連絡して指示を仰いでください。
猫の避妊・去勢手術にかかる費用について

手術費用は、地域、動物病院の設備や方針、猫の性別や体重、術前検査の内容などによって大きく異なります。あくまで一般的な目安として参考にしてください。
手術費用の目安と内訳
手術費用には、通常、術前検査料、麻酔料、手術料、術後の内服薬、エリザベスカラー代などが含まれます。費用の総額は、一般的に開腹手術が必要なメス猫の方が、オス猫よりも高額になる傾向があります。
費用の目安は以下の通りです。
・オス(去勢手術): 15,000円 ~ 30,000円程度
・メス(避妊手術): 20,000円 ~ 40,000円程度
詳細な費用については、必ず事前に動物病院に確認しましょう。
助成金・補助金制度の活用
お住まいの自治体によっては、飼い猫の避妊・去勢手術に対して助成金や補助金を交付している場合があります。
制度の有無や申請条件、金額はお住まいの市区町村によって異なりますので、役所の担当窓口(保健所や生活衛生課など)や公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。
猫の避妊・去勢手術に関するよくある質問(Q&A)

Q. 猫の避妊や去勢はかわいそうでは?
A. 将来的な病気や問題行動のリスクを下げることで、猫にとってもより穏やかな生活が送れるようになります。
Q. 室内飼いの猫でも避妊・去勢は必要ですか?
A. はい。発情によるストレスや病気の予防のためにも、室内猫にも推奨されます。
Q. 手術後は性格が変わってしまいますか?
A. 穏やかになる傾向はありますが、基本的な性格が大きく変わるわけではありません。
まとめ

猫の避妊・去勢手術は、飼い主として愛猫の健康と将来を考える上で、非常に重要な選択です。手術には全身麻酔のリスクや費用といった負担が伴いますが、望まない繁殖の防止、病気の予防、問題行動の抑制など、猫と飼い主の双方が得られるメリットは計り知れません。
手術への不安は、正しい情報を得ることで大きく和らぎます。この記事で得た知識をもとに、かかりつけの獣医師と十分に話し合い、あなたの愛猫にとって何が最善の道なのかを考えてみてください。その決断が、愛猫とのより豊かで幸せな未来へとつながるはずです。
監修者プロフィール
獣医師:葛野宗
かどのペットクリニック・副院長
2009年麻布大学獣医学部獣医学科を卒業。 2015年から横浜市内で妻と動物病院を営み、犬、猫、エキゾチックアニマルの診療を行なっています。 2024年現在、犬10頭、猫3頭、多数の爬虫類と暮らしています。 愛犬家、愛猫家として飼い主様に寄り添った診療を心がけています。 内科(循環器、内分泌など)、歯科、産科に力を入れています。
記事の提供/ねこちゃんホンポ
【「ねこちゃんホンポ」について】
ねこちゃんホンポは、愛猫との生活をより豊かにするために作られた情報サイトです。「猫」に関わる幅広いテーマを展開しており、初心者の飼い主さまからベテランのキャットオーナーさままで、そしてまだ猫を飼っていない方にも、役立つような情報を発信しています。
※掲載している内容は、2025年8月21日時点のものです。
※ページ内のコンテンツの転載を禁止します。