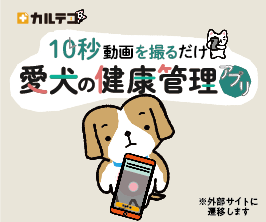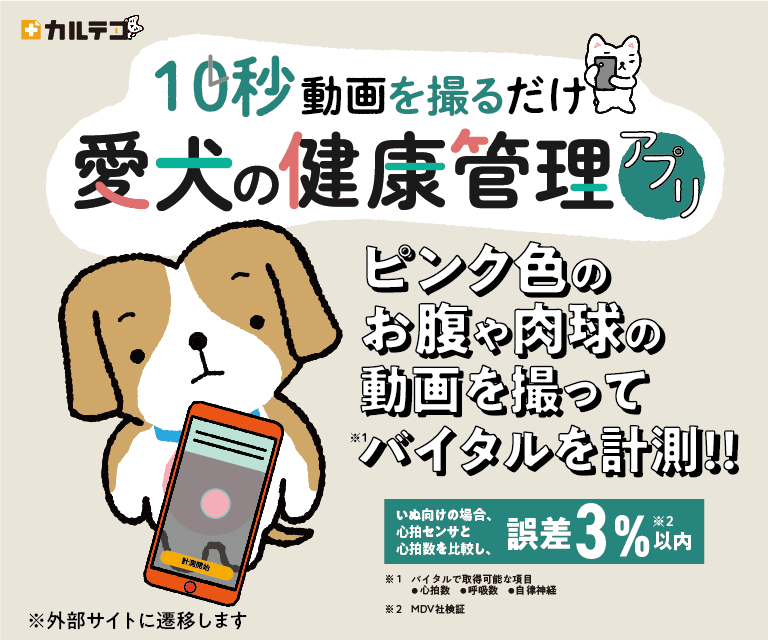大切なペットとの暮らしのためのお役立ち情報
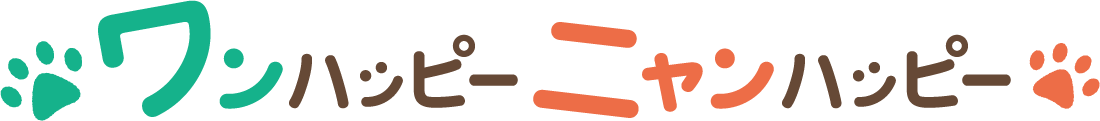
猫の生活
猫の年齢の早見表~人間の年齢での計算方法や平均寿命を解説~

家族の一員である愛猫に健康で長生きしてもらうには、ライフステージに合わせたサポートが大切です。
本記事では猫の年齢について、年齢早見表や人間換算年齢、平均寿命などについて解説します。
年齢の見分け方やライフステージに合ったお世話の方法についても紹介しますので、現在、猫を飼っている人もこれから猫を迎える人も参考にしてください。
猫の年齢の早見表|人間の年齢に換算した場合、何歳?
環境省の「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」によると、猫の年齢を人間年齢に換算する計算式は「24+(年齢−2)×4」とされています。1歳は計算式とは例外で、人間換算年齢は15歳になり、2歳では24歳、それ以降は4歳ずつ加算されていきます。
| 猫の年齢 | 人間換算した年齢 |
|---|---|
| 1歳 | 15歳 |
| 2歳 | 24歳 |
| 3歳 | 28歳 |
| 4歳 | 32歳 |
| 5歳 | 36歳 |
| 6歳 | 40歳 |
| 7歳 | 44歳 |
| 8歳 | 48歳 |
| 9歳 | 52歳 |
| 10歳 | 56歳 |
| 11歳 | 60歳 |
| 12歳 | 64歳 |
| 13歳 | 68歳 |
| 14歳 | 72歳 |
| 15歳 | 76歳 |
| 16歳 | 80歳 |
| 17歳 | 84歳 |
猫の11歳は人間換算の年齢で60歳にあたるため、シニアともいえるでしょう。この頃から寝ている時間が増える、食欲が落ちるなど老化の徴候が現れます。
老化の症状と病気の初期症状は似ているため、1年に一度は義務づけられている健康診断を受けさせ、病気に気づきやすくなるためにも愛猫と触れ合う時間を増やすように心がけましょう。
猫の寿命|平均寿命やギネス登録されている年齢

猫の平均寿命は、室内飼いかそうでないかでも異なります。
ここからは猫の平均寿命や、長寿猫としてギネスに登録されている猫の寿命についても紹介します。
猫の平均寿命
猫の平均寿命は室内飼いの猫で16歳、外出する猫で13~14歳程度といわれています。
猫全体の平均寿命は外に出るかどうかによって、2歳ほど寿命に差があることがわかります。
猫の平均寿命はあくまでも猫全体としての平均値であり、猫の種類によってなりやすい病気に違いがあるため、猫の種類によっても寿命は異なります。
ギネス登録されている長寿猫の年齢
今までで史上最長寿とギネスで認定されている猫は「クリームパフ」という名のメス猫です。クリームパフはアメリカで1967年8月3日から2005年8月6日まで、38歳と3日生きたとされています。
生存している猫(2022年時点)の中で最高齢の猫は「フロッシー」という名のサビ柄のメス猫です。1995年12月29日生まれで、認定時の年齢は27歳で、イギリスで生活しています。
2022年11月24日にギネス記録で猫の世界最高齢と認定されました。
猫の年齢の見分け方
野良猫や保護猫など、現在の年齢がはっきりとわからない猫の年齢を自身で見分けるには、歯を観察します。
子猫の場合、乳歯がまだ生えていないようであれば生後2週間程度、乳歯が生えそろっているようであれば生後2か月程度と推測できます。
乳歯は生後3か月頃から生え変わり始め、生後6~8か月頃に永久歯がそろいます。乳歯と永久歯のバランスによっても、生後何か月程度か推測することが可能です。
成猫の場合は、獣医であっても推定年齢を出すのは難しくなります。
目安としては、白くてピカピカの歯がそろっている場合は1歳以内の可能性が高く、2~3歳になると、少しずつ黄ばみが見え始めます。3~6歳になると、歯石や摩耗が見られるでしょう。
老猫になると、歯が大きく擦り減り、中には抜け始める猫もいます。歯茎に色素沈着が見られるのも老猫の特徴です。
ただし、成猫以降の歯の状態は、生活環境や食事内容によっても異なります。特に野良猫の場合は、生活環境が過酷で歯を使用する頻度が高いため、年齢よりも歯の状態が悪い可能性が高いです。
猫の年代別の注意点

「愛猫の人間換算の年齢はわかったけれど、具体的にはどんなサポートを行えばよいの?」と感じた人もいるのではないでしょうか。
ここでは、子猫・成猫・老猫に分け、年代別の注意点について解説します。
食事の量・頻度やまたたびの与え方などについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
子猫の場合
子猫の頃は、成長期のため多くのカロリーが必要になります。1日に必要なカロリーは10週齢の場合で「体重(kg)×250kcal」、20週齢では「体重(kg)×130kcal」、30週齢では「体重(kg)×100kcal」とされています。
子猫は胃や消化器官の発達が未熟で、一度にたくさんの量を食べられません。子猫用の高カロリーフードを1日4~8回に分けて与えるのがおすすめです。
また、猫を興奮状態にさせるまたたびは、子猫のうちは与えないほうがよいとされています。
ワクチン(混合ワクチン)接種の目安のタイミングは下記です。
3回目のワクチンはブースターワクチンといい、確実に免疫をつけるために行われます。
成猫の場合
成猫の場合、1日に必要なカロリーの計算式は「体重(kg)×80kcal」といわれています。人間と同じように猫によって代謝や運動量は異なるため、様子を見ながら量の調整を行いましょう。
食事を与える回数は、朝と夕の1日2回で問題ありません。肥満気味であれば量を抑える、痩せ気味であれば量を増やすなど、適切な量を与えることが大切です。
また成猫の場合、またたびを与えることに問題はありません。1回あたり0.5gを目安に与え過ぎないように注意しましょう。回数は間隔をあけながら、多くても 1週間に3回程度を目安としてください。
またたびは猫を性的に興奮させる作用があるといわれています。中には効果のない猫もいますが、成猫であっても心臓に持病のある猫や妊娠中の猫には使用しないように注意が必要です。
シニア猫の場合
シニア猫の場合、1日に必要なカロリーの計算式は「体重(kg)×70kcal」とされています。
シニア猫は、成猫に比べ寝ている時間が増え代謝も落ちるため、肥満になりやすい傾向があります。カロリーを抑えて平均体重をキープすることが大切です。
また、消化器官の衰えや一度に食べる量が減ることから、食事は1日に3~4回に分けるのがベターです。
シニア猫の場合、歯にトラブルを抱えるケースが多くなります。歯が抜け始めていないか、口臭がしないかなど、日頃から観察することが大切です。
食欲が低下している猫の中には、歯が痛くて食べることが億劫になっている猫もいるため、定期的に獣医師に歯をチェックしてもらうのもおすすめです。
またたびは体への負担になる可能性があるため、与えない方がいいでしょう。
猫の人間換算の年齢を知ることは重要
猫の人間換算の年齢を知ることは、猫も人間と同じように歳を取ることを実感するきっかけとなります。
また、人間換算の年齢を知ることで、ライフステージに合わせて栄養管理や健康管理に気を配ることができます。さまざまな準備や対策もしやすくなるでしょう。
猫は年齢を重ねると多飲多尿や口内炎、毛のパサつきなどの症状が出てきます。これらが病気によるものか、老化によるものか判断するためにも、人間換算の年齢での把握は大切です。
フードや運動量なども年齢によって適切な健康管理方法は変化するため、人間換算の年齢を把握し愛猫に合った生活環境を整えましょう。
- ※掲載している内容は、2024年2月28日時点のものです。
- ※ページ内のコンテンツの転載を禁止します。